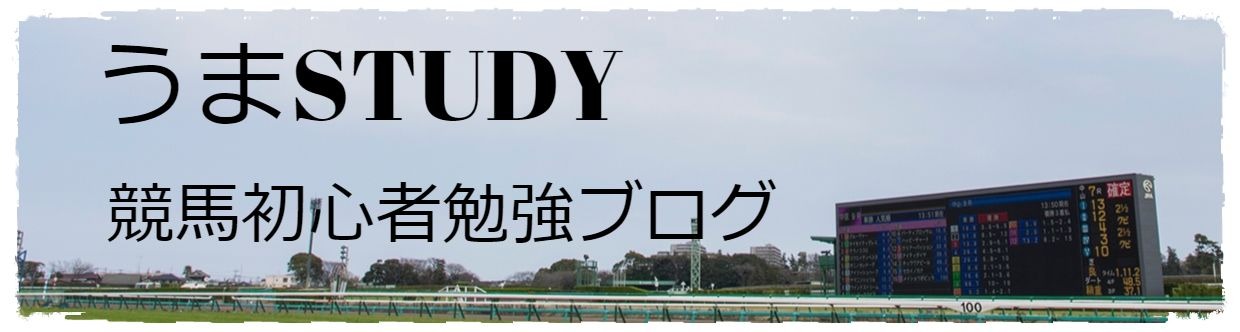連闘の評価は上げ?下げ? 連闘の意味をしっかり理解してみよう


今回は評価が難しい連闘について考えてみたいと思います。
競馬初心者の方であれば連闘と言う言葉自体知らないかもしれませんが、連闘の意味と狙えるポイントを抑えておけば、馬券成績が多少プラスになるかもしれません。
連闘とは

連闘というのは2週連続して出走させることを言います。
一般的に競走馬の出走スケジュールは1回レースで走った後は、少し休養を空けてから再度レースに挑みます。
その理由としては一回のレースでの体力の消耗や疲労の軽減が一番の目的になるのですが、中には2週連続出走(連闘)させるケースもあります。
基本的にG1などの重賞の場合にはしっかりレース間隔を取りつつ万全の体制で挑むので連闘するケースはほぼ見ないですが、下級条件に行けば行くほど連闘馬を稀に見るはずです。

騎手の都合による連闘
未勝利戦も含めて下級条件でのレースの場合は1勝でも多く勝ち星を付け、多くの賞金を得るのが調教師の目的です。

特に未勝利戦の場合にはできるだけ早く1勝クラスに上がりたいと、どの厩舎や調教師の方も思うはずなので、こういう連闘が見られるケースが多々あります。

レースを調教の一部として使う連闘

地方競馬に多いのですが、レースも調教の一部として扱っている場合があります。
中央競馬の場合はしっかりとした調教コースが備わっていますが、地方競馬の場合は基本的に当該競馬場で調教を積むことになります。
厩舎の考えにもよりますが調教をするよりもレースで実際に競走馬同士を競り合わせることが効果的として、調教感覚でレースに出すこともあるので覚えておきましょう。
その場合は連闘することを前提にして前走を使っているので、連闘馬の成績が良いケースが多いです。

北海道開催での好条件での連闘策
毎年7月から開催される夏競馬ですが、一年の中でも最も連闘が見られる期間です。
その理由の一つとして北海道で開催される、
- 札幌競馬場
- 函館競馬場
の2つについては滞在競馬が認められている点があります。
この2会場以外の開催であれば美浦トレセンと栗東トレセンからの輸送が基本になるのですが、関西から関東などの長距離輸送になると馬がストレスを感じやすくなってしまいます。
馬体重の記事にも書いていますが馬は非常に繊細な生き物なので、下級条件で走っている若駒の場合は輸送での馬体重大幅減など影響は計り知れません。
それを考えると現地滞在が可能な北海道開催は札幌と函館の行き来だけなので、輸送の面でも連闘させやすいことがわかるかと思います。
もう一つ夏競馬の特徴としては、有力馬が放牧していることが挙げられます。
春のG1シーズンが終わって夏競馬になるので、春にたくさん頑張った有力馬や秋の重賞を狙っている馬はしっかり夏の間に休養させるのがセオリーです。

連闘馬の成績からわかることとは

それでは実際に連闘した馬の成績はどうなっているかを見てみましょう。
結論から言うと、連闘馬の成績は非常に悪くなるので基本的にはあまり狙える条件ではありません。
連闘馬全体のざっくりとした成績は、
- 勝率 約5%
- 連対率 約10%
- 複勝率 約15%
- 単回値 約50%
- 複回値 約60%
となっているので、ベタ買いした場合は明らかに損することになります。
これはあくまでも連闘馬全体の成績を見ているので、その中から連闘馬でも買える条件を見つけてみましょう。
連闘でも買える条件 人気馬
まず連闘で一番覚えておいて欲しい項目として、連闘馬が上位人気の時は信頼度が上がるということ。
特に連闘馬の1番人気時の成績は、
- 勝率 約35%
- 連対率 約50%
- 複勝率 約68%
- 単回値 約90%
- 複回値 約90%
となっていて、普通の1番人気の成績よりも遥かに好成績なことがわかると思います。
1番人気も好成績ですが2番人気、3番人気などの上位人気も通常の人気よりも好成績なので、連闘馬の人気馬は信頼度が非常に高くなることに注目です。
連闘馬は一般的に評価を下げることが当たり前になっていますが、その中でも上位人気に押されるということは好走条件が整っていたり、連闘前走の内容が良かった場合や血統、厩舎から連闘が合うと判断されているということが見えます。

連闘でも買える条件 昇級初戦
連闘での昇級初戦ということは前走で勝っているということになります。
後述する馬の疲労でも書きますが、基本的に勝った馬は疲労が蓄積されやすいので連闘の場合は評価を下げます。
ただ今回の買える条件というのは、

ということです。
前走1着馬の昇級初戦が連闘だった場合の成績ですが、
- 勝率 約10%
- 連対率 約17%
- 複勝率 約26%
- 単回値 約90%
- 複回値 約95%
となっていて、先ほどの連闘馬の1番人気よりも勝率、連対率、複勝率共に落ちますが、回収率については同等かそれ以上を叩き出しています。
特に単勝については連闘馬の昇級初戦平均人気は約7番人気前後となっているので、いかに連闘の昇級馬が人気落とすかわかるかと思います。

連闘でも買える条件 北海道開催、短距離ならなお良し
最後の連闘でも買える条件としては、夏競馬の北海道開催時の連闘です。
長距離輸送が無いという部分も要因としてありますが、北海道の涼しい環境なども後押ししていると感じています。
基本的には人気馬になっている連闘馬は信頼度が高く、他の連闘馬は評価を下げるべきですが、札幌開催と函館開催の場合は評価を上げる下げるではなくフラットでいいと思います。
勝率、連対率、複勝率共に北海道開催の連闘馬は高い傾向ですが、単回値、複回値共に100%を割っていることから、北海道開催の連闘馬は他の馬券購入者に狙われている(知っている)ということがわかります。

連闘馬の距離別成績を見てみても、短距離に限っては比較的好成績です。

馬の疲労から連闘を評価してみる

連闘馬を買う時や評価する時に考える部分として、連闘レースの前レースから疲労具合を予測してみましょう。
連闘馬が北海道開催の短距離レースに出走し、上位人気で推されている状態であっても、連闘する前のレースで疲労が溜まっているのであれば好走率は下がってしまいます。
実際に厩舎(調教師)によっての連闘成績にもかなりのバラつきがあり、連闘馬をうまく扱える厩舎やうまく扱えない厩舎もデータとして読み取れます。
データから追うのもいいですが疲労が溜まる状況を理解していると、より連闘馬の評価がやりやすいと思うのでご紹介します。
疲労の溜まりやすいレース内容や脚質
競走馬が疲労が溜まるレースというのは、一言でいうと一生懸命に走ったレース。
当然ながら下級条件よりも上級条件やG1などの重賞で走った方が、持っている力を出し切るレースが多いので、クラスが上がれば上がるほど連闘が無くなるのは当然ということです。

- 上級条件レース(重賞含む)
- 消耗戦(前傾ラップ、ハイペース)
- 差し馬(上がり3F上位)
特にハイペースの展開になったレースで好走した馬は疲労が強く溜まりやすく、連闘馬で買える条件であっても割り引いて考えた方が良いかと思います。
もう一つ脚質については特に差し馬が疲労が強く出やすく、上がり3F上位であれば全力で脚を使うので疲労度合いが大きくなりやすいです。
疲労が溜まりにくいレース内容

ここからは連闘馬の前走レース内容の疲労度から、評価を上げてもいいと思える条件について書いてみたいと思います。
端的に条件を書いていきます。
- スローペースの逃げ、先行馬の勝ち馬
- レースで好走できていない(参加できていない)馬
疲労が溜まりにくいレース内容としてはこれ以外にも色々ありますが、最も配当妙味が大きく連闘を狙う上でわかりやすい2つを挙げていきます。
スローペースは基本的に瞬発力戦になることが多いレース質ですが、連闘馬の前レースとして非常に狙いやすい条件です。
理由としてはスローペース自体が前目の馬に有利な条件に加えて、開催初週などのトラックバイアスも合わさっての勝利であれば、能力を発揮せずに勝っている馬が当然います。
展開が恵まれ、枠が恵まれ、馬場に恵まれる馬であれば、疲労も溜まっていないので当然連闘でも好走できる条件が整っていると考えるのが普通です。

レースで好走できていないというよりも、レースに参加できていない馬が特に該当するのですが、レースがハイペースであってもそのペースに参加していなければペースは関係ありません。
脚質的に差し馬などの上がりで勝負する馬であっても、前が壁になってしまって脚を使っていなければ当然疲労は溜まりません。
簡潔に表すと、
- 出遅れ含め不利や前が壁などのアクシデントに巻き込まれた馬は、連闘時に穴を空けやすい
- 出遅れや前が壁などの場合は、馬券購入者の怒りが見込めるので、連闘時に配当妙味が生まれる
出遅れや前が壁というのは状況的にしょうがない場合でも、騎手のせいにする方が一定数いますし、次走は絶対買わないと思う方も出てくるはずです。

結果的に配当妙味が見込めるので、狙えるポイント
行動経済学と競馬は非常に密接に関係していて、理解しているだけでも多少は勝ちやすくなります。
連闘の評価のポイント まとめ

今回は連闘馬について簡単にまとめてみましたが、多少は連闘馬への評価方法がわかったでしょうか?
簡単に記事の内容をまとめると、
- 連闘馬は基本的に評価を下げる
- 連闘でも人気している馬は、信頼度高い
- 昇級初戦の連闘馬は人気が落ちていても狙い目
- 北海道開催、短距離が連闘馬のキーワード
- 馬の疲労を予測することで、連闘馬の評価が可能
- アクシデントで沈んだ馬は、連闘時に評価を上げるのが旨い